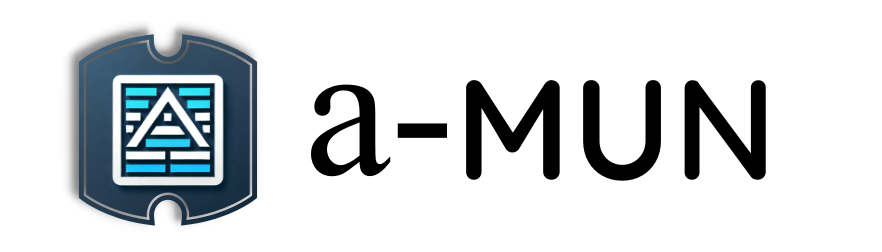【Solidity】第9章第9回:DeFiレンディングプラットフォームの構築
本記事では、Solidityを用いてDeFi(分散型金融)におけるレンディングプラットフォームを実装する方法を解説します。貸し手と借り手がスマートコントラクトを介して直接取引できる仕組みを作成し、安全で透明性のある金融システムを構築します。
0. 記事の概要
この記事を読むメリット
- DeFiレンディングの仕組みを理解: スマートコントラクトを用いた貸し借りの仕組みを学べます。
- 貸付機能の実装: Solidityを用いて貸し手・借り手の取引システムを構築できます。
- 安全な金融システムの設計: 担保管理や利息計算を適切に実装する方法を学べます。
この記事で学べること
- DeFiレンディングの基本概念
- Solidityを用いた貸付・借入システムの実装
- 担保管理と清算処理の仕組み
1. DeFiレンディングの概要
1.1 DeFiレンディングとは?
DeFiレンディングは、中央管理者を介さずに仮想通貨の貸し借りを行う仕組みです。スマートコントラクトを利用することで、安全で透明性のある金融取引を実現します。
1.2 DeFiレンディングの流れ
DeFiレンディングプラットフォームの基本的な流れは以下の通りです:
- 貸し手: スマートコントラクトに資金を預け、利息を得る。
- 借り手: 担保を預け、一定の金利で資金を借りる。
- 清算プロセス: 借り手が担保を返済できなかった場合、担保が自動清算される。
2. Solidityでのレンディング機能の実装
2.1 資金の貸付
// DeFiレンディングの基本コントラクト
pragma solidity ^0.8.0;
contract LendingPlatform {
mapping(address => uint256) public deposits;
function deposit() public payable {
require(msg.value > 0, "Deposit must be greater than 0");
deposits[msg.sender] += msg.value;
}
}
動作解説
- ユーザーが
deposit()を呼び出し、資金を預け入れる。 - 預けた資金は
depositsマッピングに記録される。
2.2 担保管理と清算処理
// 担保の管理と清算処理
function liquidate(address borrower) public {
require(deposits[borrower] > 0, "No collateral available");
deposits[borrower] = 0; // 担保を清算
}
動作解説
- 担保を設定した借り手が、返済できない場合に
liquidate()を実行。 - スマートコントラクトが担保を清算し、借り手のデポジットをリセット。
3. セキュリティと拡張性
3.1 利用者保護のための対策
DeFiレンディングの安全性を高めるため、以下の対策を導入します:
- 過剰担保の設定: 市場の変動に備え、借入額を担保額以下に制限。
- 清算条件の明確化: 借入額が一定以上になると自動清算を実行。
4. 練習問題
以下の課題に挑戦し、DeFiレンディングの理解を深めましょう:
- 貸し手に利息を分配する機能を追加してください。
- 借り手が返済可能なスケジュールを設定できる機能を追加してください。
5. まとめ
本記事では、Solidityを用いたDeFiレンディングプラットフォームの基本構造を解説しました。適切なセキュリティ対策と拡張機能を加えることで、安全で透明性の高い貸付システムを構築できます。